<ISL Paperbacks 4>
人事・総務担当者のためのメンタルヘルス読本 鈴木安名 著
新書判・189頁/850(本体810)円
<目次>→こちら
著者の図、講演スライド、各種マニュアル、および本書の補足文章が読者のみなさまにだけ無料でDLできます。
→こちら(このページにアクセスするには本書をご購入のうえ、ユーザー名:isl-mental、パスワード:本書の下段バーコード下の13ケタの数字を入力してください)
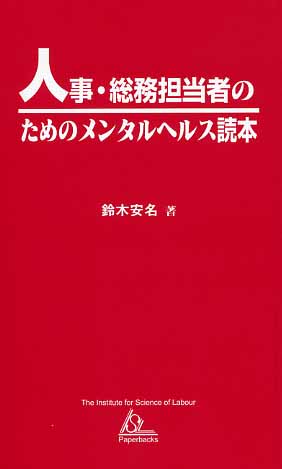
わが国でメンタルヘルスが問題になっているといっても、現場の管理職にとっては他人事です。うつ病が増えたとはいっても、診断書が出て1ヵ月以上休職する社員(職員)は全体の1〜2%です。圧倒的多数の管理職にとって、部下のメンタル休職は年賀はがきのクジに当たるようなもの。
でも皆さんは違いますね。人事、総務あるいは労働安全衛生に携わる方々にとって、当たる確率は高く、時には仕事のストレスともなります。社員300人の社で、もし30日以上心の病気で休む人が年間3名いたとすれば、それはみんな皆さんの肩に背負わされるのです。
筆者は講演などで「メンタルヘルスはどこでも悪化していますよ〜」と話しますが、役員や現場の管理職にとっては気の休まるコメントでしょうが、問題に直面している担当者にとってみれば、気休めの言葉にもならないでしょう。「私の仕事、何とかしてくれよ。ただでさえ忙しいんだ!これ以上仕事を増やさないで〜!」というのがホンネでしょう。
でも目の前の仕事をこなさなければならない。で、本(メンタルヘルス本は300種類近く出版されています)を読む。時には高いカネと時間をかけて、セミナーに参加する。でも、「どうもピンとこないな」とか、「理屈はわかるけど、わが社にはそんな予算や人材はナイよ」、あるいは「私ら、メンタル問題だけにかかわるヒマはないのだ」と、欲求不満を抱えて会社に戻る。そして、またまた休職の診断書が出て、今度は現場の管理職から「俺はどうすれば良いんだ?」と泣きつかれる。
「これは、やばいかも……」と思っても、役員クラスは関心はないか、あったフリはしても「君に任せた」というわけですが、例によって予算はほとんどつかない。
そりゃそうですよね、会社は利益を追求する場であって、リハビリセンターではないから。
でも、皆さんは日々仕事をこなさなければならない。中には、少数派でしょうが、「メンタル問題を自分のスキルアップにつなげよう」という先見の明のある方もおいでかもしれません。
そんな皆様のために、この本を書きました。できることから着手して、ご満足がえられるようなツール化、マニュアル化に努めたつもりです。特に、保健職のマンパワーが乏しく産業医が機能していない事業所で、メンタルヘルス対策が立てられるよう実用的に書きました。
〜「はじめに」より〜
↑最上端へ
第1章 経営の視点からメンタルヘルスを考えよう!
第1節 メンタルヘルス氷山の三角 (1.休職・欠勤の増加 2.ミスや事故の増加 3.犯罪とモラールの低下
第2節 企業収益への悪影響 (1.労働日数の喪失 2.仕事の能率低下とミスの増加 3.傷病手当・医療費の増加 4.自殺等への訴訟費用など 5.うつ病対策は企業収益に貢献する)
第3節 自覚症状は〈3つの「い」〉 (1.眠れない 2.食べたくない 3.だるい、疲れやすい 4.心の症状〜仕事に行きたくない〜 5.うつ病になっても自分では気づかない 6.発病の仕組み 7.うつ病になりやすいタイプ)
第4節 発見のための〈ケチな飲み屋サイン〉 (1.欠勤、遅刻・早退 2.泣き言をいう 3.能率の低下 4.ミスや事故が増える 5.辞めたいと言い出す 6.〈ケチな飲み屋サイン〉の状況)
第5節 受診の勧め
第6節 日々のメンタル対策 (1.あいさつ 2.眠れる? ――自分の脳を守る改善活動 3.職場のストレス対策の実例)
・事例・高学歴者の挫折 ・事例・月曜日の欠勤 ・事例・持ち帰り残業とアルコール依存 ・事例・超多忙職場のストレス対策
第2章 メンタルヘルスの実務
第1節 病名の意味と主治医との交流 (1.病名の意味 2.三者面談 3.三者面談をするときのポイント)
第2節 休職中の社員との情報交換 (1.休職時の連絡方法の取り決め 2.職場情報の提供)
第3節 職場復帰の判定 (1.復職診断書の導入 2.適切な復職プログラムをつくる 3.どの部署に復帰させるかは慎重に 4.職場復帰判定基準(例))
第4節 復職後の対応法 (1.担当者の対応 2.上司の業務面での対応)
第5節 安全配慮義務と個人情報の保護 (1.安全配慮義務は債務 2.プライバシーの保護 3.担当者の立場とは?)
第6節 メンタルヘルスと就業規則 (1.復職の判断は慎重に 2.休職期間満了のリセットへの対応 3.復職希望者に対する実務的対応 4.就業規則の改定 5.労務提供能力の判断は慎重に)
第7節 迷惑をかけて攻撃的なケース
・事例・長期休業 ・事例・裁量労働は外す ・事例・通算して2年半の休職の後、復職成功 ・事例・思い切って転職して成功 ・事例・プライバシーの保護と本人の了解 ・事例・職場をかき乱す社員
第3章 産業医をプッシュする (1.嘱託産業医の機能度チェック 2.産業医の労務管理 3.交渉手順 4.交渉の内容(例) 5.産業医と接する2つのポイント 6.ともに学べる場をセッティング
第4章 対策の実践 (1.構えずにできることから 2.どんなことが可能か? 3.メンタルヘルス勉強会を企画する 4.トップへの訴えと合意形成)
第5章 Q&Aと理解度チェック (1.メンタルヘルスQ&A 2.メンタルヘルス理解度チェック)
【問1】どうみても復職困難な社員について、主治医が「復職可能、ただし軽勤務から」という診断書を出してきました。主治医の判断に従わなければならないのでしょうか? 【問2】産業医や保健師、カウンセラーなどから、社員との面談内容を聴きたいのですが、どうすればよいのでしょう? 【問3】リセット的な復職をした社員への対応について 【問4】事業所に顔を出さない産業医には、どう接すればいいの? 【問5】担当者として疲れきっているし、これ以上仕事を増やす余裕はない感じだ。むしろ自分自身がメンタル不全かも……どうすればいい? 【問6】自らメンタルクリニックを受診して、「うつ病」という診断書を振りかざし、特別扱いを求める社員がいます。どう考え、接したらよいでしょうか? 【問7】心の病気と仕事の能力との関係については? 【問8】「自分はストレスがたまっている」と言い、感情的になって同僚や上司にカッターナイフを突きつけることを2度した社員がいます。メンタル不全かもしれないので、どう対応すればよいのか困っています。 【問9】医療機関への料金支払いはどうすればよいのですか?
付録1.リーフレット「メンタルヘルスのすすめ」
付録2.頼りになる相談機関(連絡先)